「広告のタネ 2」
第6回 ネタが六分で、技三分…
雑誌編集の世界はいつも大忙し
僕は、コピーライターとして広告の仕事をしていますが、最近は雑誌に取材原稿を書くという仕事が増えています。
雑誌づくりは、まずエディター(編集者)が、こんな本をつくりたいというヴィジョンを掲げます。「巻頭の特集ページはこんな内容で…」とか「連載のレギュラーページでは、今回これをネタに…」といった企画を立てるわけです。この企画に基づいて、エディターは取材をして原稿を書いたり、写真を撮ったり、デザイナーと打ち合わせをしたり、といった諸々の仕事をしていきます。
このほかにも会社によって違いはありますが、営業担当者との打ち合わせ、印刷会社との打ち合わせ、コストの管理、流通(販売)関係の対応、取材協力者への贈呈本の発送など、種々雑多な仕事があります。
本来、これらの業務は雑誌を出版している会社のなかで行うべきものですが、人的コストやクオリティのことを考えると、外部の専門家に発注したほうがメリットが大きい場合があります。特に、写真やデザインや文章は、それぞれの分野に専門家がいますから、彼らや彼女らの力を借りて本(雑誌)をつくったほうがより魅力的な本をつくることができるわけです。
料理の世界とライター業の共通点
以上のような構造の中で、僕は取材ライターの仕事を出版社から委託されて行っています。ライターの仕事は、エディターから指示された取材先に出掛け、現場の雰囲気を伝えたり、関係者にインタビューしてその声をまとめていくもので、基本的にはレポートが主な仕事です。
僕がいつも仕事をいただいている雑誌は大人向けの情報誌で、飲食店や温泉、さらには文化財までさまざまな物件を対象に取材を行い、原稿を書いていきます。
当然、いろいろな世界の人とお話をするわけですが、もっとも共感するのはシェフや板前といった料理人の皆さんです。
なぜ、料理人に共感することが多いのかというと、料理の世界とライターの世界はとても似ていると思うからです。多くの料理人は食材を求めて買い出しに出掛けます。これはライター業でいえば取材に相当します。
取材から帰ると、ライターは録音した取材対象者の声をノートにまとめたり、資料を見直したりします。この作業をしながら、どういうふうに原稿を書いていくかを決定していきます。このネタは、どんなふうに料理すればお客さま(読者)においしく召し上がっていただけるか、ということを考えていくわけです。
料理の方向性が決まると、調理(原稿執筆)に取りかかります。後は、出来上がった料理を皿に盛りつければ一応の完成となります。皿に盛るとは、規定の文章量に収めていくということです。雑誌の場合、あらかじめ全体で何文字でとか、天地00文字(一行あたりの文字数)×左右00行(全体の行数)でといった規定がありますから、この条件をクリアしなければなりません。ちなみに、パンフレットなどの広告の場合も最初にデザイン案がある場合は、同じような指示があります。こんな具合に、職種は違っても料理人とライターの基本は似たところが多いのです。
ときどき僕がつくった料理(雑誌原稿)は、取材先の人から褒められることがあります。そんなとき、いつも思うことは「今回はネタが良かったから」ということです。結局、「ネタが六分で、技三分」だと僕は思います。ネタ本来の旨味を生かしながら、食べやすく加工してあげること。僕たち職人の使命はそこにあるのだと思います。
という話を、取材先のある寿司屋さんでしたら、とても共感していただきました。あ、「ネタが六分で、技三分」には続きのフレーズがあります。「あとの一分は運しだい(笑)」。ネタと技術と運。旨い料理(上手い雑誌原稿)に欠かせない3要素です。
profile
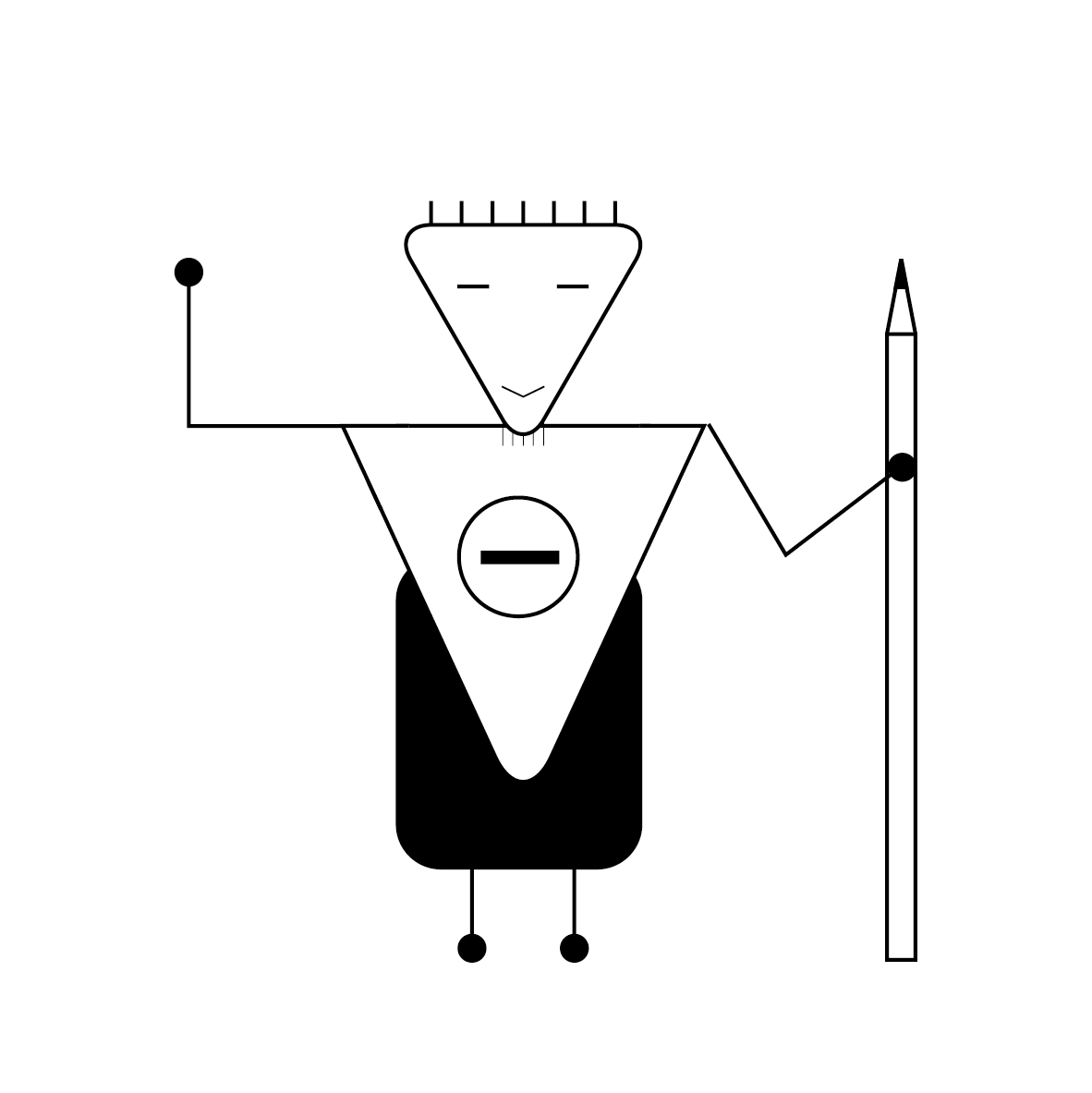
一丸幹雄 氏
(いちまる・みきお)
昭和30年、大分県杵築市生まれ。
日本大学法学部新聞学科卒業。㈱宣伝会議「コピーライター養成講座」一般コース・専門コース修了後、東京の広告制作会社に勤務。昭和56年にUターン後、大分市の広告代理店、制作会社に勤務。県内各企業の広告や行政の広報、雑誌の取材・執筆を手がける。 現在、フリーランスとして活動中。


