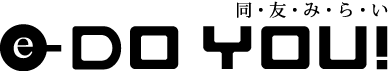大塚は「東京ローカル」のトップランナー目指すのか/Long Distance Love 〜東京より熱烈な愛を込めて #43
冒頭から、そもそも「東京ローカル」って何?という話ですよね。
最近はあまり使われなくなりましたが、例えば東京及び関東一部でしか放送されないテレビ番組(地上波)のことを「東京ローカル番組」と呼んでいました。東京も全国47都道府県のひとつに過ぎないという、ちょっと謙遜した言い方かもしれません。
 その一方で、何もかもが一極集中している世界的大都市・東京にローカル(田舎的要素)なんてあるのか?って話ですが、前回の「亀有」に続いて、今回は東京ローカル最前線(?)を行く街「大塚」をご紹介したいと思います。
その一方で、何もかもが一極集中している世界的大都市・東京にローカル(田舎的要素)なんてあるのか?って話ですが、前回の「亀有」に続いて、今回は東京ローカル最前線(?)を行く街「大塚」をご紹介したいと思います。
東京人(在住者)にもちょっと分かりにくのが、「大塚」は豊島区と文京区にまたがっていること。
ちなみに駅(北大塚・南大塚)は豊島区、「大塚」(本家?)は文京区というからややこしい。
 同じ豊島区でも一大歓楽街、最近ではシン・サブカルの聖地&芸術都市を目指す「池袋」と、“お婆ちゃんの原宿”から近年は若い女性たちにも大人気の「巣鴨」に挟まれ、地味な東京ローカル人生を歩んできた大塚が一躍脚光を浴びるきっかけは、日本どころか世界的ブームまで巻き起こしている、おにぎりブームの火付け役『ぼんご』の存在でしょう。
同じ豊島区でも一大歓楽街、最近ではシン・サブカルの聖地&芸術都市を目指す「池袋」と、“お婆ちゃんの原宿”から近年は若い女性たちにも大人気の「巣鴨」に挟まれ、地味な東京ローカル人生を歩んできた大塚が一躍脚光を浴びるきっかけは、日本どころか世界的ブームまで巻き起こしている、おにぎりブームの火付け役『ぼんご』の存在でしょう。
大塚駅北口を出て徒歩数分、平日休日・時間帯を問わず終日大行列のこのお店、一時は3時間待ちもザラでした(というか、おにぎりを食べるのにこんなに待てる人が凄い‼)
でもこの程度で大きく取り上げることは出来ないわけで、実は今この街にとてもユニークでいて、亀有同様、不安を感じさせる注目すべき動きが2つあります。
一つ目は、批評家・宇野常寛が東邦レオ(本社大塚)と共同プロデュースする「宇野書店」が8月に正式オープンすること。
「町の本屋が減少の一途を辿っていることに危機感が募らせる」彼がすべてセレクトした書籍のみを並べて販売する」この書店は、いわゆる大塚に関わる人達みんなの拠り所として、彼の主張する「コミュニティ創出」ではなく、大塚発の国内ローカル(規模を問わない地方都市)へ拡大展開するリアルなビジネスプラットフォーム「シン・書店」として構想している点がとてもユニークです。

 もう一つの、ちょっと悪い意味で気になるのが「ironowa ba」プロジェクトなる不穏な動き。
もう一つの、ちょっと悪い意味で気になるのが「ironowa ba」プロジェクトなる不穏な動き。
簡単に言うと「まちをカラフルでユニークな“場”に変えていく」地域活性化プロジェロジェクトらしいですが、別に大塚以外でも使えそうな言い回しがいかにも代理店的。さらに「ba」の意味は「being &association /いることとつながること」「そこに行けば、人や街とのつながりを感じる場になる」という想いが込められているらしい。
さらに意味不明なのが「地域の体温を上げる:大塚を36.9℃のワクワクが起こる街にしよう」というコンセプト。最近のまちづくり系再開発の中でもダントツに抽象的かつ曖昧なコンセプトですが、調べてみると主体は地元で長く続く不動産管理会社の若き代表者のようです。細かい経緯は割愛しますが、どうやらパッとしない地元大塚の活性化のため、外部からブランディングディレクターを招き、星野リゾートやチームラボと手を組み、駅前に謎めいたタワーのある「ironowa hiro ba」を作り、周辺のホテル・商業・オフィスビルから雑居ビル(「ぼんご」が入居)に至るまで、「ba01」から「ba07」等の番号サイン(看板)が付けられ、街と一体化どころか違和感だけが残る結果になってしまっているような気がします(個人的見解です)。

 こうした試みを一概に否定することは出来ませんし、あくまでも地元住民や来街者の反応・判断に委ねられるべきとは思います。
こうした試みを一概に否定することは出来ませんし、あくまでも地元住民や来街者の反応・判断に委ねられるべきとは思います。
個人的には最初に紹介した「宇野書店」は大きくて派手なプロジェクトではありませんが、大塚という街の身の丈に合った、でも大きなポテンシャルを秘めているプロジェクトだと強く感じます。
そう、先日訪れた時も「亀有」同様、インバウンドも少なく、ちょっとホッとしたことを、ここに書き添えておきます。
profile
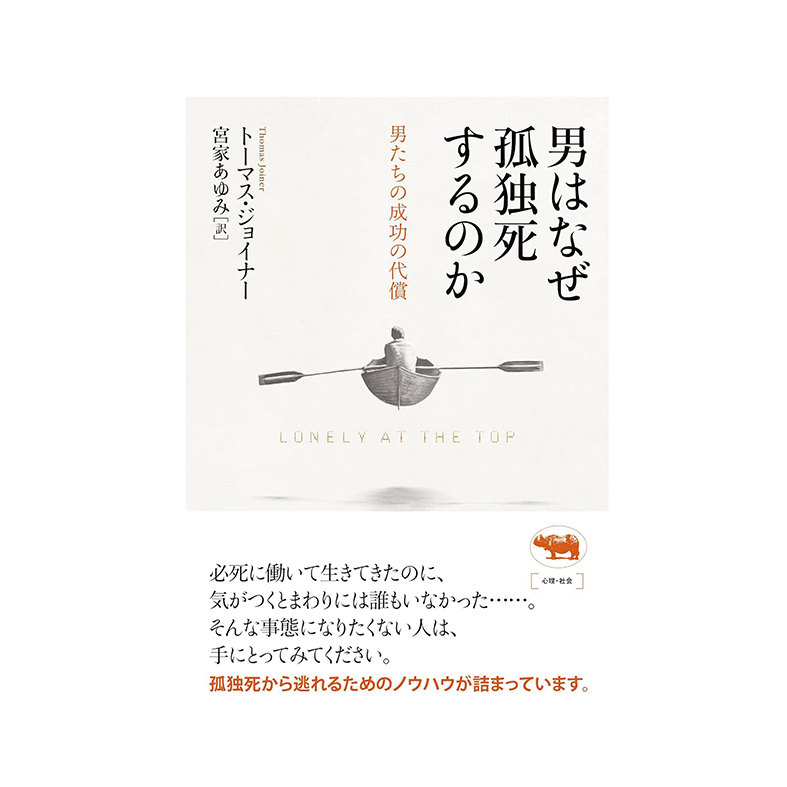
しばた・ひろつぐ/1960年、福島県郡山市生まれ。筑波大学を卒業後、1983年株式会社パルコ入社。2004年〜2007年には大分パルコ店長を経験。2018年2月に独立し「Long Distance Love 合同会社」を設立。
■Long Distance Love合同会社
https://longdistancelove.jphttps://amzn.asia/d/dmwpJhH
「男はなぜ孤独死するのか/男たちの成功の代償」を最後まで読もうと思った意外なキッカケ
本文でも紹介した東京ローカル「大塚」にオープン予定(2025/8/1) の批評家宇野常寛がプロデュース&セレクトする本のみを取り扱う書店「宇野書店」の内覧会で偶然目に止まり、勢いで買ってしまたのがこの本。
大手企業でサラリーマン生活を送った経験を持つ自分にとって、タイトルには「男」「孤独(死)」「成功の代償」等、いかにも不快感・不安感を抱かせるワードが並んでいて、今までの自分だったら絶対買わない、手にも取らなかったであろうこの本。一体何がキッカケだったんだろうとあの時を思い起こしてみると…。
いきなりですが、ここでちょっと脇道に逸れます。この後に続く文章はChatGPTに「この本の感想(要約文)を書いて!」とオーダーしたもの。実は読み始めたもの、内容以前に翻訳(の文章)がピンと来なくてページが進まず、そのためにChatGPTに助けを求めたところ、以下のようにまとめた文章が出てきました。
要するにこの本は、
「現代社会における男性の生き方や価値観を鋭く問い直しています。」
「成功や社会的地位を追求する男性たちが、時にその代償として孤独や人間関係の疎外感に直面することを探求しています。」
「著者は、男性が社会的期待やプレッシャーの中でどのように振る舞い、どのような選択をするのかを深く掘り下げ、なぜ孤独に至るケースが多いのかを丁寧に紐解いています。」
「この本は、男性自身にとってももちろん重要ですが、彼らを取り巻くパートナーや家族、同僚といった人々にも新たな視点を提供します。」
「成功だけが人生の目的ではないことを示し、バランスの取れた生き方を模索するための指針となるこの一冊は、男性のみならず幅広い読者にとって価値ある知見をもたらすもの。」
らしいです。
そう、実はこの「まとめ」のおかげで、かつての自分に当てはまることがたくさんあると気付かされたわけです。そして不快・不安に感じたワードを客観的かつ冷静に捉えられる気がしたことも確かです。
その後は読みにくい翻訳文にも負けずに読了できました。
こんな使い方もあるんですね、ChatGPT。