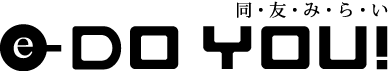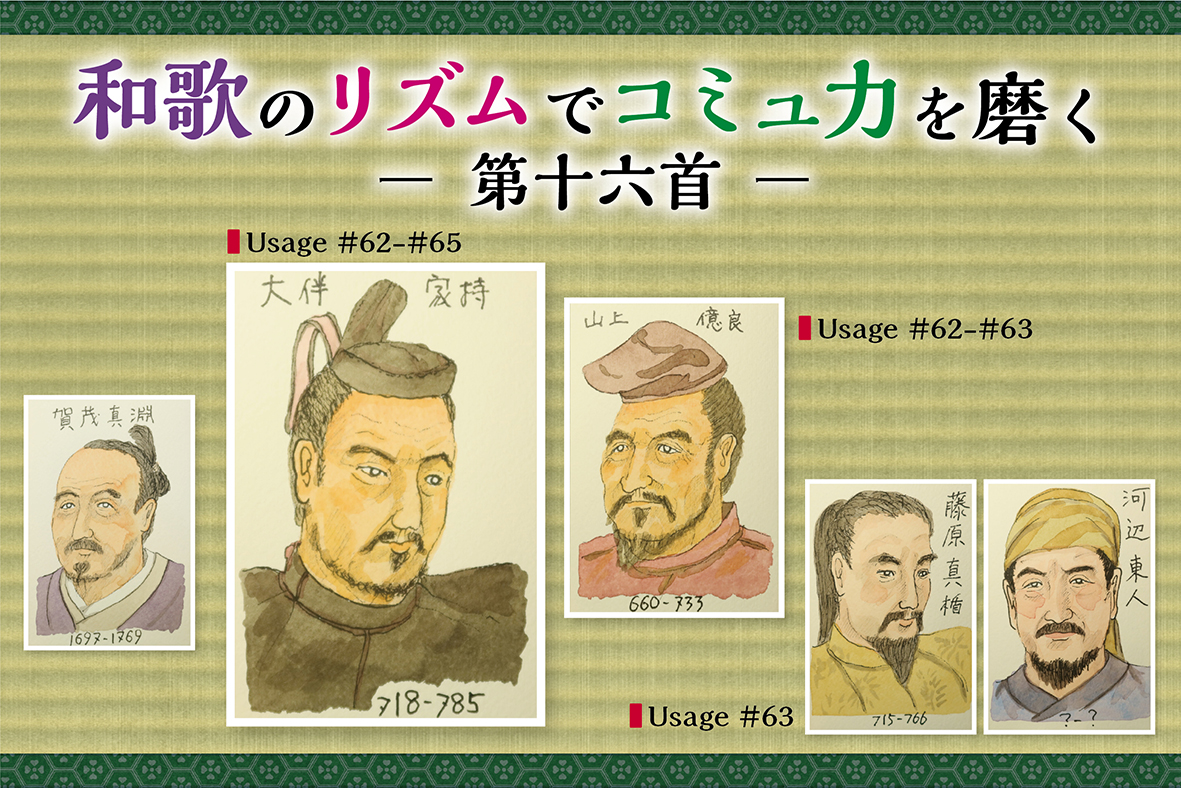
「ますらをぶり」は男子っぽいという意味、「たをやめぶり」は女子っぽいという意味。
これ、高校の古文で習いました。
で、50年以上、そうなんだと思ってました。読みもせず(笑)。
でも、ちょっと読んでみると「この分け方って大雑把すぎません? 言い出しっぺの賀茂真淵さんよ」という気がします。
今回は「ますらを」という言葉は入っているけれども、言ってることは「たをやめぶり」、という歌を手はじめに、万葉の歌を四首セレクトしました。
幸せに生きるためのヒントになれば幸いです。
【和歌のスタイルで表現してみた】
■Usage #62
心の休憩も大事よ、の法則
男子たるもの名を上げなければ よろしきけれど重きときは下ろしてヨシ
[元歌]
ますらをは名をし立つべし 後の世に聞き継ぐ人も語り継ぐがね 万4165
訳:男子たるもの、名を立てるべきだ。後世、その名を聞いた人が語り継げるように。
[解説]
これは大伴家持が詠んだ山上憶良のカバーソング(笑)。今思ふと、半世紀前はみーんな貧乏でした。でも勢いがありました。今はちょっと停滞気味かな。そんな時代ですから「ますらを(の自負)」が重いと感じたら、荷を下ろして一息入れてはいかがでしょう。休みながら進むのが遠い道を歩く秘訣、と言いますから。
* * *
■Usage #63
重荷は下ろすと楽になる、の法則
自分の考え方が重いと感じたら 下ろして一服が効果あり
[元歌]
をのこやも空しくあるべき 万代に語り継ぐべき名は立てずして 万978
訳:男子たるもの、世を空しく過ごして良いものか。後世に語り継がれるほどの名を立てないまま。
[解説]
これが家持の4165番歌の元歌。最晩年の山上憶良が病気で床から起きられなかったとき、藤原真楯の遣いで病状伺いに来た河辺東人に憶良が涙ながらに伝えた一首だそうです。憶良という人、情に厚く気配りが利き、淡々としているように見えるけれど、実は芯が強く自分に厳しい人物だったようです。だって、そろそろ死ぬかも、というときにこんな歌、謳えます? 「ますらをぶり」や「たをやめぶり」とかを合わせた次元にいらっしゃる。
* * *
■Usage #64
安定志向はリスク、の法則
この世は移り変わる 目の前のことに打ち込むべし
[元歌]
うつせみの常なき見れば 世間に心つけずて思ふ日ぞ多き 万4162
訳:この世はどんどん変わる。その様子を見ていると、仕事に集中できずぼーっとする日が多くなる。
[解説]
これは家持の歌。この世が移り変わるのは、家持の時も、今も変わりません。ぼーっとすると言いながら、家持はいくつもの乱にかかわるほど行動が活発でした。一息ついたり、ぼーっとする。これが変化の流れに溺れないコツかも。
* * *
■Usage #65
花の寿命は季節区切り、の法則
花や葉が散るごとく 時が来れば人は去るのが世の常
[元歌]
世間は数なきものか 春花の散りのまがひに死ぬべき思へば 万3963
訳:広い世界では自分などものの数にも入らない。春に散る花のようにこの世を去る存在と思うと。
[解説]
これも家持の歌。「世間は数なきものか」の解釈が難しいです。そこで適当に自分の好きに受け取りました。「死ぬ」という恐怖のワードが目立ちます。その前に「春花の散りのまがひに」があります。花は四季の中で命を全うするのに対して人の寿命は、はるかに長い。しかし終わりは來る。だからこそ花の散りが気になるのでしょう。
profile

あべ・ひろふみ:1953年、大分市生まれ。大分大学教育学部物理学科卒業、師匠は田村洋彦先生(作曲家)。由布院温泉亀の井別荘天井桟敷レジデント弾き語リスト(自称)。大分大学で第1号の経済学博士、指導教員は薄上二郎先生(現青山学院大学経営学部教授)。国立大学法人電気通信大学客員教授。電通大認定ベンチャーNPO法人uecサポート理事長。
■Facebook https://www.facebook.com/hifofumi.abe/
■電通大認定ベンチャーNPO法人uecサポート https://uec-programming.github.io/uec_support/