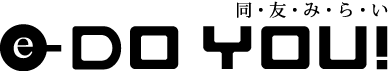言葉は心が現れるので、TPOに応じた適切な言葉とリズムでコミュニケーションできる人になりたいですよね。
今回は、お別れのときに感じる寂しい気持ちの表し方。
これを先人はよき言葉とリズムで表しています。マネしてコミュ力を磨きましょう。
【和歌のスタイルで表現してみた】
■Usage #70
別れの寂しさは素直に認めるのが良き、の法則
会おうと思えばいつでも会える でも別れは寂しいもの
[元歌]
天雲の行き帰りなむものゆゑに 思ひぞ我がする別れ悲しみ 万4242
訳:空の雲のように行き帰りは簡単、とはいえお別れは悲しい。
[解説]
なぜ、別れのときは寂しい気持ちになるのだろう。次に会うまでの時間が今までより長くなるからだろうか、、、わからん。
この歌の作者は藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ/706 – 764)、またの名を恵美押勝(えみのおしかつ)。この人、ブイブイ言わせた時期もあり、乱を起こして負けて斬首の経験もした、人生完全燃焼の人。
* * *
■Usage #71
目的達成と無事帰還の両方を祈るのが良き、の法則
かの国に行き足らはして帰り来む ますら健男に御酒奉る
[元歌]
唐国に行き足らはして帰り来む ますら健男に御酒奉る 万4262
訳:唐の国でのミッションを達成したら帰って来る立派な男子に乾杯。
[解説]
先日、米国に留学した若者に歌を贈りました。「かの国」を「米国」に替えて。異国で外国語で勉強する気概の持ち主なので、ますら健男(たけを)が相応しいと思いました。女子の場合なら「たをやめ娘子」で行けそう。
歌の作者は多治比鷹主(たじい の たかぬし/? – ?)。アンチ藤原仲麻呂が集まって起こした橘奈良麻呂事件に加わり捕まったあげく拷問死を経験。
* * *
■Usage #72
お別れの場面では餞を贈るのが良き、の法則
わたつみの海行きしかば海人の 我に得しめし海づとぞこれ
[元歌]
あしひきの山行きしかば山人の 我れに得しめし山づとぞこれ 万4293
訳:私が山に行ったとき、山の住人がくれた山の土産です、これは。
[解説]
昔から人はお別れのとき何かプレゼントしていたので、この歌を選びました。餞別の「餞」は「旅に出る人などに贈る、品物・金銭や詩歌」とのこと。モノを渡す時、歌や物語を添えるとよろしいようで。
この歌の作者は元正天皇(げんしょうてんのう/680 – 748)。独身で即位した初めての女性天皇。
* * *
■Usage #73
別れの悲しい気持ちは正直に出すのが良き、の法則
豊後の後には逢はむしましくも 別るといへば悲しくもあるか
[元歌]
能登川の後には逢はむしましくも 別るといへば悲しくもあるか 万4279
訳:後ほどまた、と言いましょう。お別れと言うとちょっとの間でも悲しいから。
[解説]
元歌は「能登川」は「のと」を後(のち)にかけた言葉遊び。これに倣って「豊後」で行ってみました。後も豊か。とてもめでたい。下の句の「別るといへば悲しくもあるか」はまさにその通り、言い得て妙。
元歌の作者は船王(ふねおう/? – ?) 奈良時代の皇族。橘奈良麻呂事件では多治比鷹主と反対の立場で謀反者の拷問を担当。
profile

あべ・ひろふみ:1953年、大分市生まれ。大分大学教育学部物理学科卒業、師匠は田村洋彦先生(作曲家)。由布院温泉亀の井別荘天井桟敷レジデント弾き語リスト(自称)。大分大学で第1号の経済学博士、指導教員は薄上二郎先生(現青山学院大学経営学部教授)。国立大学法人電気通信大学客員教授。電通大認定ベンチャーNPO法人uecサポート理事長。
■Facebook https://www.facebook.com/hifofumi.abe/
■電通大認定ベンチャーNPO法人uecサポート https://uec-programming.github.io/uec_support/